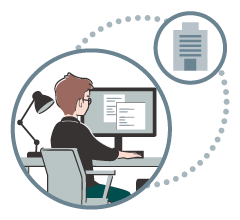内臓冷え(隠れ冷え)に注意!~夏こそ温活しよう~
2021年7月暑さと共にエアコンが欠かせなくなり、かき氷やアイスなど冷たいものがおいしい季節になってきましたね。
今回は、夏バテや風邪を予防するためにも気をつけたい「内臓冷え」についてご紹介します。
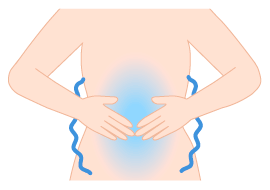
内臓冷えって何?
内臓冷えは、隠れ冷えや夏冷えとも呼ばれていて、手足や肌の表面は温かくても内臓が冷えている状態をいいます。みぞおちやおへその周りなどを触ってみて、手よりもお腹の方が冷たい場合は、内臓冷えを起こしていることになります。
自分が冷えていることに気づいていない人も多いため、疲労感やだるさ、肩や腰が重いなどの不調があっても原因として思い当たらず、そのまま放置されてしまうことも少なくありません。
内臓冷えの原因
自律神経の乱れ
自律神経は、活動時に働く交感神経と、リラックス時に働く副交感神経の2つがバランスを取って交互に作用し、内臓の働きや血液の流れ、発汗などを制御しています。しかし、何らかの原因で自律神経のバランスが崩れると、身体にさまざまな不調が現れます。内臓冷えの場合は、主に副交感神経が過剰に働くことで、寒いときでも手足の血管が収縮しにくくなるため、熱が放出され続けてしまい、手足は温かいのにお腹が冷たい状態となってしまいます。
自律神経のバランスが乱れる原因には、ストレスや疲労の蓄積、不規則な生活習慣などがあります。また、夏特有の原因として、冷房のきいた室内と暑い屋外との温度差が挙げられます。温度差の大きい場所を1日に何度も行き来すると、その度に自律神経が体温を調節しようと発汗などの制御を行うため、自律神経に負荷がかかり、バランスが乱れてしまいます。
同じ姿勢や悪い姿勢・運動不足による血行不良
デスクワークなどで長時間、同じ姿勢を取り続けたり、姿勢が悪かったりすると血流が滞って冷えやすくなります。ずっと同じ姿勢を取っていると血行が悪くなるのはもちろんですが、姿勢が悪いと特定の部位の筋肉に負担がかかり、筋肉が固まってしまい血行不良になってしまいます。そのため、なるべく良い姿勢を取るようにして、こまめに立ったり、伸びをしたり、足首を回したりして血行を促進しましょう。
また、運動不足による筋力低下も冷えの原因になります。悪い姿勢は楽ですがその分、筋力は衰えてしまいます。背中やお腹、太ももなど大きな筋肉をきちんと使って座るようにしましょう。それだけで代謝が上がり、身体を温めることができます。
冷たいものの摂りすぎ(コールドドリンク症候群)
夏は特に気をつけたいのが、冷たい食べものや飲み物の摂りすぎです。コールドドリンク症候群とも呼ばれ、冷たいものをたくさん摂ると、一時的に胃が低温になり、その温度が胃の周りの毛細血管に伝わって血液の温度まで下げてしまうため、全身が冷えることをいいます。さらに胃の周りの温度が低い状態が続くと、脳が「寒いから胃腸を守るために脂肪を貯めよう」と勘違いしてしまい、お腹周りに脂肪が蓄積しやすくなるため、ポッコリお腹を招くことにもなります。
また、夏は薄着になるため、冷房で冷えすぎてしまうこともあります。外出する際は、羽織るものを持ち歩きましょう。寒がりな人は薄い腹巻をするのもおすすめです。そのほか、シャワーのみでお風呂を済ませると、身体の深部が温まりきらないため、できるだけお湯につかるか、難しければ足湯を取り入れたり、シャワーで仙骨(お尻の真ん中にある逆三角形の骨)を温めたりするなどの工夫をしましょう。
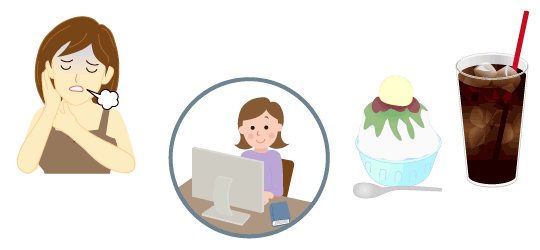
内臓冷えが起こるとどうなる?
血行不良
全身の血流が滞ることで、体の隅々まで栄養や酸素が行き渡らなくなって熱を生み出す力が低下します。肩こりや腰痛、生理痛なども起こりやすくなります。
代謝の低下
代謝が悪くなると、エネルギー消費量が減って太りやすくなります。また、体内の余分な水分を排出しにくくなるため、むくみやすくなります。
免疫力の低下
腸には、身体中の免疫細胞のうち、60~70%程度の免疫細胞が存在しますが、腸が冷えると免疫細胞の働きが弱くなるため、免疫力が低下します。そのため、風邪をひきやすくなったり、アレルギーを起こしやすくなったりします。
自律神経の乱れ
自律神経のバランスの乱れは内臓冷えの原因でもありますが、内臓冷えによっても、より一層、自律神経は乱れてしまいます。そのため、頭痛や気分の落ち込み、不眠などが起こりやすくなります。
消化機能の低下
血流が悪くなることで、胃の消化機能が低下したり、腸のぜん動運動が弱くなって便秘を起こしたりします。反対に、冷たいものの刺激によって腸の働きが活発になりすぎて下痢を起こすこともあります。これらの消化機能の低下は、食欲不振の原因にもなります。
夏バテ
食欲不振になって、タンパク質や脂質が不足すると、エネルギーが生み出せず夏バテを起こします。その結果、頭痛やめまい、倦怠感や疲労感などの症状が現れます。
内臓冷えしていませんか
さわってみよう
実際に自分のお腹をさわって、冷えていないか確かめましょう。心臓の辺りや、みぞおち、おへその周りなどをさわってみてください。手の温度よりもお腹が冷たくなっていませんか?
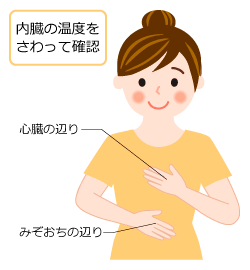
内臓冷えセルフチェック
- □アイスなどの冷たいものを食べたり飲んだりすることが多い
- □清涼飲料水や甘いものが好き
- □運動習慣がない
- □1日中デスクワークで座っている時間が長い
- □なんとなく不調がある
- □湯船にはつからずシャワーで済ませる
あなたは、いくつチェックがつきましたか?
1つでもチェックがついた方は、「内臓冷え」を起こしている可能性があります。
温活のすすめ
内臓冷えは、とにかく温めることが大切です。身体を外側と内側の両方から温めましょう。簡単にできて夏でも続けられる、おすすめの温活をご紹介します。
- 朝食を食べる
- アイスやサラダ、ヨーグルトなど冷たいものを食べるときは、温かい飲み物を飲む
- 1日の食事のどこかに味噌汁やスープをプラスする
- 温活効果のある食材を取り入れる(生姜、ねぎ、鮭、青魚、甜菜糖、黒糖など)
- 発酵食品を積極的に食べる
- 38~40℃の少しぬるめのお風呂にゆっくりつかる
- お風呂の後や寝る前にストレッチをする
- 座っている時間が長い場合は、こまめに立ったり、足を動かしたりする
- ウォーキングなど適度な運動で筋力アップ
- おなかの周りを温める
- 腹式呼吸をする
暑いときは、熱中症対策を強く意識してしまいますが、必要以上に体を冷やさないように気をつけましょう。温活は、夏バテ防止や免疫力向上など、良い効果がたくさんあるので、ぜひ試してみてください。
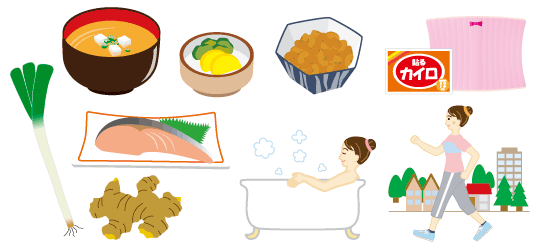
これからの季節、意外と見落としがちな「内臓冷え」。
体を温める習慣をつけて、代謝を上げ、暑さに負けない体づくりをして夏を乗り切りましょう。
来月のテーマは、「腸内環境 ~新しい生活様式~」です。
生活・健康のリズムに
興味がある方は
文部科学省後援 健康管理能力検定3級・2級
健康管理のスペシャリストを
目指す方は
健康管理士・文部科学省後援 健康管理能力検定1級
category
- 季節の健康(35)
- 今話題の健康ワード!(13)
- 日本の郷土料理(48)
- ハーブ・アロマと健康(13)
- おいしさの秘密(12)
- ストレス解消法(13)
- 世界の人々の暮らし(12)
- 体に必要な「ミネラル」ってなんだろう??(12)
- 行事食(12)
- 四季を感じる食と食養生(27)
- 香りのパワーでこころとからだをリフレッシュ(8)
- こころがもたらす体のサイン(8)
- 今日からはじめる健康づくり(17)
- 気になる症状におすすめの食材(18)
- スリム&きれいに(8)
- 気になるからだの危険信号(45)
- 自然治癒力を高める(11)
- 健康診断・生活習慣病(9)
- 感染症(13)
- 新しい生活様式(10)
- 筋肉をもっと知ろう(11)
- 何気ない不調の解消法(12)
- 病気について知る(6)