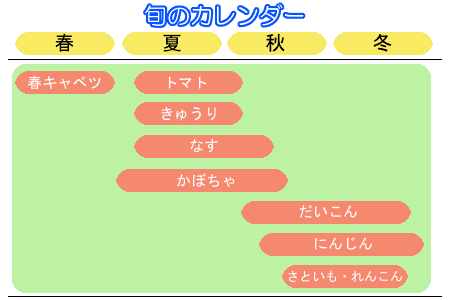美味しく!ゆるっと!「心と体を整えよう」
2025年9月号 秋になると「食欲が止まらない」「なんだか眠い」「やる気が出ない」など不調を感じることはありませんか?
秋になると「食欲が止まらない」「なんだか眠い」「やる気が出ない」など不調を感じることはありませんか?
今回は、この時期に現れやすいこれらの不調について解説するほか、旬の食材やゆるっと運動を取り入れる方法についてご紹介いたします。
秋は、心も体も不調になりやすい
秋は夏に比べ日照時間が短く、朝晩の冷え込みなどによって自律神経が乱れやすくなる他、ホルモンバランスにも影響を与えるため、さまざまな症状があらわれます。
日照時間と食欲・睡眠の関係
日照時間が短くなると起こるのが、気分を安定させるセロトニンの分泌量の減少です。セロトニンは、脳内で働く神経伝達物質で、通常、材料となるトリプトファンやビタミンB6、そして、朝の太陽の光を浴びることによって合成されます。しかし、トリプトファンなどの材料が不足したり、朝の太陽の光を浴びる量が少ないと、セロトニンが不足してしまいます。
このように、セロトニンが不足すると、炭水化物や甘いものに対する食欲が増す傾向にあると考えられています。これは、糖分を摂取すると放出されるインスリンに、トリプトファンが脳内に運ばれるのを促進する働きがあるためです。また、セロトニンの分泌が減少すると、気分の落ち込みや不眠などを引き起こすこともあります。
日照時間が短くなっても、朝陽をしっかりと浴びることでセロトニンを原料とする睡眠ホルモンのメラトニンの分泌をサポートすることができます。
気温や気圧の変化
夏から秋にかけて気温や気圧が変化すると、体は変化に適応しようとして自律神経が乱れやすくなります。例えば、外気温が低い時は、自律神経のうちの交感神経が優位な状態となり、血管を収縮させて熱の発散を防ぎ、血流を減少させて体内から熱を逃げないようにしたり、熱を産生する方向に働きます。このような状態が続くと、エネルギーの消費が多くなるため、疲れやダルさといった症状につながってしまいます。
秋は代謝が上がって痩せやすい?!そのメカニズムとは
先ほどご紹介したように、季節の変化によって不調を招きやすい一方で、秋の特徴を味方につけることで代謝アップにもつながります。
外気温の変化
秋になると気温が下がりはじめます。気温が下がると体は体温を維持するために、熱を生み出し一定に保とうとします。熱を生み出す際に、より多くのエネルギーを使うようになるため、9~12月にかけて、エネルギーの消費量が増えやすい傾向があります。
眠りに最適な条件が増える
秋は、本能的に寝る時間が長くなる傾向があります。メラトニンは暗くなると分泌が促されるという特徴があり、日照時間が短く秋の夜長といわれるように、夏に比べ暗くなるのが少し早めるため、メラトニンの分泌時間も早まり、夏よりも眠りやすくなると考えられます。また、睡眠は気温や湿度に大きく左右されますが、秋の夜間の気候は快適な温度・湿度に近いとされています。
睡眠は、夏の暑さなどに耐えてきた体を癒すために有効的です。睡眠中に分泌される成長ホルモンには、ダメージを受けた細胞の修復や再生を促し、体の疲れを回復させる効果があります。その他、脂肪の分解を促進し、脂肪燃焼を助ける働きもあります。
代謝の味方!秋の味覚を味方につけよう
秋に旬を迎える食材には、エネルギーや脂肪の燃焼、さらには心を穏やかにしたり、睡眠や気分を整える栄養素がたくさん詰まっています。夏の暑さによって消耗した体の回復させ、代謝を促す栄養素をとることで代謝がさらに上がりやすくなります。旬の味を味わいながら、代謝スイッチも秋モードに切り替えていきましょう。
さつまいもやかぼちゃ
食物繊維が豊富で満腹感を得やすく、腸内環境が整うことでセロトニンが分泌されやすい環境になります。
きのこ類
低カロリーで食物繊維が豊富、そして、エネルギー代謝や疲労回復を促すビタミンB群、さらにセロトニンの活性を高めるビタミンDなども含まれています。
サケやサンマ
DHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸が豊富で、抗酸化作用によって、細胞の修復や疲労回復を促し、血管の柔軟性などを高める効果も期待できます。
栗やナッツ類
ビタミンB群、オメガ3脂肪酸のほか、マグネシウムが含まれストレス軽減につながり、心も穏やかになります。
自然を感じながら心地よく!ほどよくゆるい運動もオススメ
運動と聞くとジムにいき筋トレしたり、マラソンしたりとハードなイメージが先行しがちでが、この秋おすすめしたいのは、「自然を楽しみながら」「頑張り過ぎない」ほどよくゆるい運動です。
ポイントとは「心地よい」!
ここでおすすめしたいのが、「食べ物×運動」です。ウォーキングやランニングのルートを決める際に、中継地点やゴールに秋の味覚を楽しめるように設定してみましょう。ちょっと気持ちよい、なんか美味しい、ちょっと嬉しいが、気分も体も少しずつポジティブな方向に整えてくれます。いざ運動をする!となると億劫になる人も、楽しみがあると自然と頑張れます。ワクワクとしながら、運動ができて、心も体も満たされます。
おすすめプラン
- 焼きいも片手に、ウォーキング(散歩コースに目的やゴールを設定して散歩)
- ランニングして、ゴールの果樹園でくだもの狩り
- 公園であおぞらヨガ(落ち葉の中で深呼吸)

この秋は、秋の味覚を食べて、動いて、おいしくゆるっと整えてみませんか。
生活・健康のリズムに
興味がある方は
文部科学省後援 健康管理能力検定3級・2級
健康管理のスペシャリストを
目指す方は
健康管理士・文部科学省後援 健康管理能力検定1級
category
- 季節の健康(35)
- 今話題の健康ワード!(13)
- 日本の郷土料理(48)
- ハーブ・アロマと健康(13)
- おいしさの秘密(12)
- ストレス解消法(13)
- 世界の人々の暮らし(12)
- 体に必要な「ミネラル」ってなんだろう??(12)
- 行事食(12)
- 四季を感じる食と食養生(27)
- 香りのパワーでこころとからだをリフレッシュ(8)
- こころがもたらす体のサイン(8)
- 今日からはじめる健康づくり(17)
- 気になる症状におすすめの食材(18)
- スリム&きれいに(8)
- 気になるからだの危険信号(45)
- 自然治癒力を高める(11)
- 健康診断・生活習慣病(9)
- 感染症(13)
- 新しい生活様式(10)
- 筋肉をもっと知ろう(11)
- 何気ない不調の解消法(12)
- 病気について知る(6)