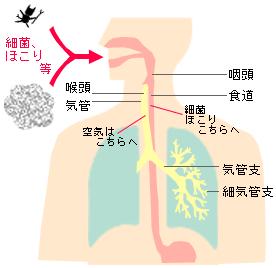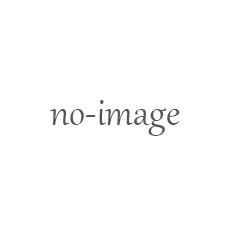だるさ -気になるからだの危険信号-
2002年4月号だるさとは

誰でも、体がだるいと感じたことはあると思います。
2~3日の休養で回復するようであれば、それほど心配はいりません。
しかし、「休養してもだるい」「激しい運動をしたわけではないのに体がだるい」という時はさまざまな病気の前ぶれであることがあります。そのため、医師の診察を受けて原因を解明することが大切です。
「だるい」の原因はさまざま
過度な運動や労働など、体を使いすぎた後に起こるだるさ(疲労)
2~3日の休養で回復するのが特徴です。心配することはありませんが、きちんと体を休めることが大切です。
何もする気になれないだるさ(うつ)
例えば、本を読んだり、テレビを見たりすることすら億劫になってしまうことはありませんか?これは精神的な原因、つまりうつ状態にあることで起こるだるさと考えられます。本人は本当にだるくてつらいのですが、他人にはやる気がないだけのようにみられがちなのが特徴です。
睡眠の質の低下によるだるさ(睡眠時無呼吸症候群)
睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間、何らかの原因で気道が閉じたり狭くなったりして、一時的に呼吸が止まっては再開するというサイクルを繰り返す病気です。睡眠の質が低下するため十分な休息が取れず、日中の眠気やだるさといった症状が現れます。また、いびきを伴うことも多いです。
感染症に伴うだるさ
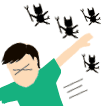
風邪をひいたときなどに体がだるくなるのは、細菌やウィルスに感染したためです。
また、風邪をこじらせた後に起こるだるさは腎炎であることがあり、だるさと同時に、むくみや頭痛、血尿やタンパク尿、高血圧、吐き気、食欲不振といった症状が現れます。
酸素の供給不足によるだるさ(貧血、心臓病)
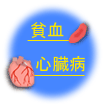
ちょっとした階段の昇り降りなどでもだるいと感じることがあり、このようなだるさは貧血や心臓病によって起こっている可能性があります。
貧血にはいろいろな種類がありますが、この場合は、赤血球に含まれる血色素(ヘモグロビン)が足りなくなって起こる貧血が関係しています。血色素が不足すると、酸素が十分に全身へ運ばれなくなるため、筋肉への酸素の供給が不足して体が思うように動かず、階段の昇り降りなどでもだるいと感じるのです。
また、中高年の場合は心筋症や弁膜症、心筋梗塞の前ぶれといった、心臓病が原因となることもあります。血液を全身に循環させている心臓のポンプの能力が低下するために下半身がむくんだり、だるかったり、体を動かすと息切れがしたりします。
血液の成分変化によるだるさ(肝炎)
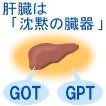
肝炎とは、肝臓が炎症を起こし肝細胞が破壊された状態で、急性と慢性に分けられます。急性肝炎は、発熱やだるさ、食欲不振や黄疸といった症状が現れますが、慢性肝炎は、だるさなどの自覚症状がある場合もありますが、ほとんどの人は自覚症状が無く、健康診断で見つかることが多いです。血液検査の結果、GOT(正常値:10~40(IU/l))、GPT(正常値:5~35(IU/l))の値が高ければ、肝臓の機能が低下していることになります。肝臓の機能が低下すると、十分な量のエネルギーが生成できなかったり、体内のアンモニアなどの有害物質を解毒しきれなかったりするため、だるさが生じます。
肝炎のほかに、ある種の血圧降下剤や漢方薬を長期にわたって飲み続けた場合も、血液中の成分変化によってだるさが起こることもあります。特に高齢者に起こりやすいので、日ごろから注意してください。
※GOT、GPTの正常値は各医療機関・検査機関や検査方法になどによって若干の違いがあります。
栄養の低下によるだるさ(糖尿病、がん)
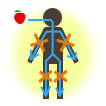
糖尿病では、摂取したエネルギー源が体内で適切に使用できず、だるさを感じます。だるさと同時に、喉が渇いたりやせたり、頻尿や多尿がみられたりする場合は、糖尿病を疑いましょう。
また、がんでは、がん細胞が体内の栄養分を奪ってしまうために栄養不良となって、だるさが起こります。だるいという症状の自覚が、がんの早期発見につながる可能性もあるため、やはり注意が必要でしょう。だるさと同時に食欲不振がみられる場合には、胃がんの可能性も考えられます。
甲状腺機能の異常によるだるさ(甲状腺機能亢進症・低下症)
首元にある甲状腺では本来、新陳代謝を促進する甲状腺ホルモンが必要な分だけつくられていますが、自己免疫疾患などが原因で甲状腺ホルモンがつくられすぎたり、足りなかったりすると身体中にさまざまな影響が及びます。
甲状腺ホルモンが多すぎる場合は甲状腺機能亢進症、少なすぎる場合は甲状腺機能低下症と呼ばれ、そのどちらにも共通してみられる症状が、だるさや疲れやすさ、顔・全身のむくみや抜け毛、甲状腺の腫れです。また、甲状腺機能亢進症に特有の症状は、頻脈や動悸、多汗、不眠やイライラ、体重減少、下痢などで、甲状腺機能低下症は、徐脈や低体温、眠気、体重増加や便秘などがみられます。
自律神経の乱れによるだるさ
自律神経には、身体を活動モードにする交感神経と、休息モードにする副交感神経があり、それらがバランス良く作用することで、内臓の働きや血液の流れ、発汗などを正常に保っています。しかし、過度なストレスや不規則な生活習慣などが原因で、交感神経の働きが強まった状態が続くと、だるさや不眠、不安、食欲低下や腹痛などが起こります。特に思春期の子どもは、身体の発達に伴って自律神経のバランスが崩れやすいので、注意が必要です。
何の原因も思い当たらないだるさ(慢性疲労症候群)
慢性疲労症候群は、正式名称を「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)」といい、それまで健康に生活できていた人が突然、社会生活や日常生活に支障をきたしてしまうほどの重度の疲労感に襲われる病気です。診断が難しく、原因不明のため治療は対症療法となります。だるさのほか、微熱や頭痛、睡眠障害や認知機能障害、リンパ節の腫れ、関節痛、低血圧などがみられ、うつや不安障害などの精神疾患を併発することもあります。
だるさを伴う病気としては他にもいくつかあります。
発熱を伴う場合
肺炎、膠原病(慢性関節リウマチ)が考えられます。
頭痛や肩こりがひどい場合
疲れ目(眼精疲労)が原因です。
40~50歳代の女性の場合
頭痛や肩こり、ほてりなどを伴う場合は、更年期障害が考えられます。
休養しても回復しない時…病院で検査を受けよう
だるい、と思ったら、まずは休んでみましょう。2~3日の休養で治るようであれば、過労やちょっとしたストレスによるところが多いでしょう。
しかし、休養してもだるさがとれず、チェックポイントに思い当たる点があれば、ただちに検査を受けましょう。 検査を受けるかどうかのポイントは次のとおりです。
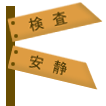
- 休養すれば治るか
- 熱はないか?
- 尿の色が変わっていないか?
- 歩行や階段などで同じ歳くらいの人についていけるか?
- 体重が減っていないか?
- 長期にわたってのんでいる薬はないか?
なかでも発熱は、体の中で何かが起きているというサインなので、慎重になる必要があります。また、尿の色にも注意しましょう。紅茶をうんと濃くしたような色ならば、肝臓の病気が考えられます。
また、同年代の人に比べて疲れやすい、最近体重が減ったなどという場合も深刻な病気が隠れている可能性もあるので、単なるだるさと軽んじず、まずは内科で診てもらいましょう。
来月のテーマは、「うつ病 -気になるからだの危険信号-」です。
生活・健康のリズムに
興味がある方は
文部科学省後援 健康管理能力検定3級・2級
健康管理のスペシャリストを
目指す方は
健康管理士・文部科学省後援 健康管理能力検定1級
category
- 季節の健康(35)
- 今話題の健康ワード!(13)
- 日本の郷土料理(48)
- ハーブ・アロマと健康(13)
- おいしさの秘密(12)
- ストレス解消法(13)
- 世界の人々の暮らし(12)
- 体に必要な「ミネラル」ってなんだろう??(12)
- 行事食(12)
- 四季を感じる食と食養生(27)
- 香りのパワーでこころとからだをリフレッシュ(8)
- こころがもたらす体のサイン(8)
- 今日からはじめる健康づくり(17)
- 気になる症状におすすめの食材(18)
- スリム&きれいに(8)
- 気になるからだの危険信号(45)
- 自然治癒力を高める(11)
- 健康診断・生活習慣病(9)
- 感染症(13)
- 新しい生活様式(10)
- 筋肉をもっと知ろう(11)
- 何気ない不調の解消法(12)
- 病気について知る(6)