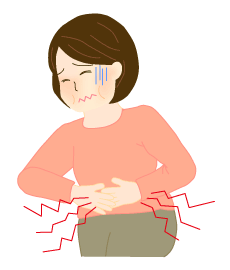日焼け止めはなぜ必要?適切な使用で疲労軽減?!
2025年8月号①日に日に陽ざしが強くなり、みなさまも暑さ対策に加えて、日焼け止めや日傘、サングラスなど紫外線対策にも力が入ってきているのではないでしょうか。
紫外線は、肌にダメージを与えるだけでなく、疲労感にも関わっていると言われています。
今回は、「日焼け止めの働き」のほか「日焼け」と「疲労」の関係について解説いたします。

なぜ日焼け止めが必要なの?~紫外線による肌へのダメージ~
日焼けは、いわば「紫外線によって引き起こされる『軽い火傷』の状態」です。たとえ短時間であっても、紫外線対策や保湿ケアを怠ってしまうと、下記のようなトラブルの原因になることもあります。
- 赤くなったりヒリヒリと炎症を起こす
- 肌細胞を守るために作られるメラニンという色素によってシミになる
- 肌細胞の深くまで傷つけ、炎症を起こしシワなどの肌トラブルの原因となる
そして、最悪の場合には肌細胞のDNAを傷つけ、皮膚がんなどの原因となることもあります。

日焼け止めは、このような紫外線からの肌ダメージ(火傷)を防ぐためのスキンケア用品です。
主に、「紫外線吸収剤」と「紫外線散乱剤」の2種類の成分が使われており、クリームタイプがメジャーですが、ジェルや乳液タイプ、髪まで使えるようなスプレータイプまであります。
また、化粧下地やファンデーション、リップクリームといった化粧品にも紫外線カット機能が備わっているものが多く存在します。
日焼けは疲れる?!~疲労感を招くメカニズム~
海水浴などに行き、煌々と照り付ける太陽の元で1日過ごした翌日、どっと疲れが出たという経験はありませんか?
適度な日光浴を行うことは、セロトニンの分泌を促し、私たちの免疫力を維持するのに必要なビタミンD生成に欠かせません。ところが、紫外線を浴び過ぎてしまうと、体にとっては大きなストレスとなり、体内では活性酸素が生成されます。活性酸素は、病原体やウイルスを攻撃するなど生理機能の維持のために重要な役割を果たしていますが、必要以上に増えると体内での酸化反応が過剰となり、神経細胞にダメージを与えてしまいます。
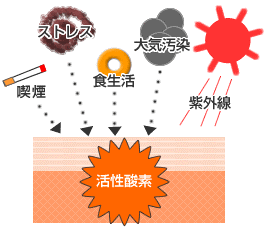
自律神経の乱れ
目から入った紫外線は、脳に刺激を与えます。長時間続くことでストレスとなり、大量の活性酸素を発生させます。少量であれば、体内の抗酸化防御機構によって恒常性(ホメオスタシス)を維持することができますが、過剰な活性酸素は神経細胞を酸化させ、機能が障害されやすくなってしまいます。
さらに、紫外線は、交感神経を刺激することでさらに活性酸素の生成を促進します。身を守ろうと自律神経がバランスをとるために働きが活発になりますが、やがて自律神経が疲弊し、疲労感だけでなく様々な不調を招くという悪循環に陥る可能性があります。
ダメージの修復
日焼けによる肌の炎症を抑えるために、エネルギーや血流が使われ、体力を消耗することも挙げられます。その他、日光に当たることで体温が上昇し、体温を維持するために汗をかくことで体内の水分が奪われ、脱水状態になり、血流が悪くなることで疲労物質の排出が遅れたり、回復のための栄養素や酸素が行き届きにくくなることも要因だと考えられます。
日焼け止めの表示の見方と選び方
ここからは、日焼け止めの表示の意味と強さ、そして、目的別の適切な選び方について解説します。
目的別!日焼け止めの選び方は、こちらの記事をチェックしてみて下さい。
食Do!食の力を味方につけるポータルサイト
「日焼け止めの効果と最適な選び方を徹底解説!」
https://www.shoku-do.jp/column/sunscreen/
SPFとPA
- SPF (Sun Protection Factor)
SPFは赤くなりにくさの指標です。肌が赤くなったり、ヒリヒリする日焼けは、主に紫外線の中でも波長が短いUV-Bによるものです。SPFは、このUV-Bの防止効果を数値化したものです。「SPF1」を約20分としてその効果の持続時間を表しており、最高値はSPF50ですが、それ以上の効果があるとされる場合には「SPF50+」と表記されます。例えば、SPF15と表記されている場合には、20分×15₌約5時間紫外線を防ぐことができます。
- PA (Protection Grade of UVA)
PAは黒くなりにくさの指標です。主に紫外線の中でも波長の長いUV-Aによるもので、肌の奥深く真皮層まで届き、シワやたるみなど肌老化の原因となります。UV-Aの防止効果は「+(プラス記号)」によって4段階で示され、「+」の数が多いほど防御効果が高いことを表しています。
UV耐水性(ウォータープルーフ)
SPFやPAに加え、汗や水に対して強く落ちにくいという意味合いで「ウォータープルーフ」という言葉が使われていました。しかし、これまで明確な基準がなく、消費者にとってはどれを選ぶべきなのか判断基準が難しいものでした。そこで、2022年12月より「UV耐水性」という統一基準の運用が始まり、2024年12月以降は、製造される製品に対しては、従来のウォータープルーフの表記は認められず、「UV耐水性」の表示が義務づけられるようになりました。
UV耐水性とは、水に浸かった後に50%以上SPFの効果を保持できるかを「★」の数で示したものです。そのため、耐水性をアピールする場合、SPFを必ず一緒に表記する必要があります。「UV耐水性★」または、「UV耐水性★★」の2段階で表され、★1つは40分の水に浸した後、★2つは80分水に浸したの後50%以上効果が保持されることを示しています。
水に濡れたり、汗をかいても落ちにくいメリットというメリットがあります。海やプールでのレジャー時やスポーツの時に向いている半面、クレンジングなどを使用し、丁寧に洗わないと落ちにくく、洗い残しによる肌トラブルが起こることもあり、使用後のケアには注意が必要となります。
日焼け止めは夏だけ塗ればよい?
紫外線は1年を通して降り注いでいるため、季節に限らず塗り続けるのが望ましいといわれています。季節によっては、夏ほど紫外線量は多くないため、時期に応じた強さを使い分けるようにしましょう。また、季節だけでなく塗り心地や肌質に合わせ使いやすいものを選ぶことも大切です。
- 夏6~8月
1年間で最も紫外線量が多くなるため、SPFやPA値の高いレベルのものを選びましょう。また、汗をかくと日焼け止めの効果が落ちてしまうこともあるため、2~3時間おきにこまめに塗り直しをすることも大切です。塗り直しには、スプレータイプやパウダータイプなどを活用すると手軽に塗り直しができるためおすすめです。さらに、海やプール、屋外でのレジャーやスポーツの際には、UV耐水性表示がついたものを選ぶとよいでしょう。
- 秋9~11月
紫外線量は夏ほど多くないものの、気候がよくアウトドアやBBQ、ランニングなど屋外での活動が多くなる行楽シーズンでもあります。日常的には、SPF30、PA+++程度の数値のものを選び、長時間屋外で過ごす場合には、夏と同様の強さのものを選ぶようにしましょう。また、空気が乾燥し始める時期でもあるため、保湿成分が含まれているものを選ぶのもよいかもしれません。代表的な保湿成分には、セラミドやヒアルロン酸、スクワランなどがあります。
- 冬12~2月
長袖を着て、肌の露出が少なく、紫外線量も比較的少ない時期です。日常生活では、SPF15~30程度、PA++程度の低めの低刺激で、保湿効果の高いものを選ぶようにしましょう。また、スキンケアとしても保湿を意識することで肌の負担を軽減させることができます。ウィンタースポーツなど長時間屋外で過ごす場合には、雪の照り返しなどにより紫外線量が増えるため、夏と同様にSPFやPA値の高いものを選ぶようにしましょう。
- 春3~5月
紫外線量が徐々に増えてくる時期であり、冬の肌の露出が少ない時期から、薄着となり紫外線を浴びる機会が増えてきます。さらに、花粉が飛散したり、空気の乾燥したりと肌の状態が敏感になり、ゆらぎを感じやすい時期でもあります。春は、肌の乾燥が気になりやすくなるため、保湿成分が配合された、SPF25、PA値は++程度で敏感肌でも使える低刺激なものを選ぶとよいでしょう。さらに、花粉やほこりなどが肌へ付着しにくいものを使うことで、肌の刺激を防ぎ、花粉症対策にもつながります。
生活・健康のリズムに
興味がある方は
文部科学省後援 健康管理能力検定3級・2級
健康管理のスペシャリストを
目指す方は
健康管理士・文部科学省後援 健康管理能力検定1級
category
- 季節の健康(35)
- 今話題の健康ワード!(13)
- 日本の郷土料理(48)
- ハーブ・アロマと健康(13)
- おいしさの秘密(12)
- ストレス解消法(13)
- 世界の人々の暮らし(12)
- 体に必要な「ミネラル」ってなんだろう??(12)
- 行事食(12)
- 四季を感じる食と食養生(27)
- 香りのパワーでこころとからだをリフレッシュ(8)
- こころがもたらす体のサイン(8)
- 今日からはじめる健康づくり(17)
- 気になる症状におすすめの食材(18)
- スリム&きれいに(8)
- 気になるからだの危険信号(45)
- 自然治癒力を高める(11)
- 健康診断・生活習慣病(9)
- 感染症(13)
- 新しい生活様式(10)
- 筋肉をもっと知ろう(11)
- 何気ない不調の解消法(12)
- 病気について知る(6)